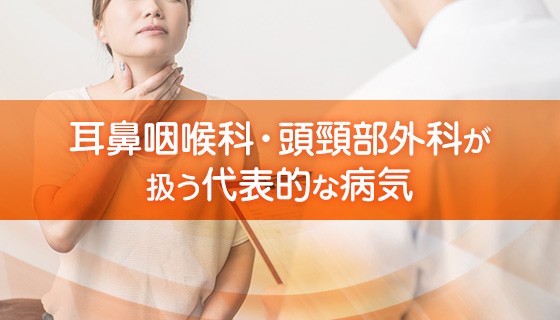耳がかゆい
耳のかゆみが起こる原因としてはほとんどの場合が外耳炎によるものです。外耳道の皮膚は皮下組織が非常に薄く、刺激に弱いため、耳掃除などでも容易に炎症を起こしてしまい、かゆみを生じる原因となります。かゆみが治まらない場合や悪化して痛みが生じる場合、耳だれが生じる場合には耳鼻咽喉科での治療が必要となります。
耳が痛い
耳の炎症から起こった痛みとして頻度の多いものには鼓膜の奥の中耳に炎症を起こしている急性中耳炎や鼓膜自体に炎症を起こしている鼓膜炎、鼓膜の手前の外耳に炎症を起こしている外耳炎などが挙げられます。その他、先天性耳瘻孔は生まれつき耳の前などに穴が開いていて、そこに感染がおこることで痛みが生じます。水痘・帯状疱疹ウイルスに感染した炎症の場合は、激しい痛みを感じることがあります。また、外傷や外耳道異物、腫瘍などでも痛みを生じる場合があります。耳の周囲や耳の中の神経痛もあります。これは短く鋭い痛みを繰り返す特徴があります。痛みだけでなく顔面の運動麻痺(顔面神経麻痺)やめまいなどを同時に起こしている場合には、緊急の処置が必要となることもあります。
上記の他、耳以外の場所が原因で耳の痛みが生じる場合も少なくありません。顎(がく)関節は耳の穴のすぐ前にあるため、顎関節症による顎の痛みを耳が原因と思ってしまうことがあります。また、中耳は耳管という管を通して咽頭と繋がっており、同じ舌咽(ぜついん)神経という神経が感覚を支配しているため、のどの炎症でこの神経が刺激されて耳が痛いと感じることもあります。
耳だれが出る・耳が臭う
「耳だれ」は耳から流れ出る液体、もしくは液体の出てくる状態のことで、耳漏(じろう)ともいいます。「耳だれ」があると外耳道や中耳の病気の可能性があります。発生する原因によって漿液(しょうえき)性、膿性、粘液性、粘膿性、水様性、血性などと性質が異なります。外耳道から発生する「耳だれ」は、外耳道湿疹や耳かきのしすぎによるものは漿液性で、細菌感染を起こすと膿性になります(外耳炎)。また、外耳道の柔らかい耳あかが「耳だれ」に似ている場合がありますが、これは体質によるもので病気ではありません。中耳から発生する「耳だれ」は、中耳粘膜から生じる粘液性のもので、細菌感染を起こすと粘膿性になります(中耳炎)。慢性中耳炎では鼓膜穿孔を通って中耳から外耳道に流れ出ます。慢性中耳炎の中でも好酸球性中耳炎は非常に粘性の強い耳だれが出ます。外傷などが原因で髄液が外耳道に流出すると水様性になります。また、中耳や外耳道の外傷、悪性腫瘍などの疾患では、組織の破壊を伴い、血性耳漏を認めることがあります。
聞こえが悪い
「聞こえにくい」という症状は、「難聴」とも呼ばれます。難聴の起こり方は、生まれつき聞こえが悪い先天性難聴や徐々に聞こえにくくなるもの、ある日突然聞こえなくなるものまで様々です。例えば、いわゆる加齢性難聴は、両方の耳が同じように長年かけて徐々に聞こえにくくなる状態で、誰しもがいつかは経験することになります。大きな音を聞いて起こる音響外傷、叩かれたり、耳かきを刺してしまったりすることで起こる外傷性鼓膜穿孔、原因となる病気がないにもかかわらず、聞こえが悪くなる機能性難聴などもあります。片耳の難聴、急になった難聴や変化のある難聴、耳なりやめまいを伴う難聴、耳だれや耳の痛みを伴う難聴は、メニエール病や突発性難聴、中耳炎などの治療可能な耳の病気で聞こえにくくなった可能性がありますので、早めに耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。小児難聴、ムンプス(おたふくかぜ)難聴はこちら
また、難聴は認知症の予防可能な因子の中で最大の危険因子ともいわれており、難聴を放置しておくと認知症やフレイルの原因となりますので注意が必要です。補聴器の効果が期待できることが多いので「難聴」と「補聴器」の両方を熟知した日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医に相談してみましょう。
耳なりがする
耳なりは、実際には音がしていないのに、何かが鳴っている様に聞こえる現象です。一般に耳なりは、難聴とともに出現することが多いとされています。耳鳴りは本人にしか聞こえない自覚的耳鳴(じめい)と、外部から聞くことが可能な他覚的耳鳴とに分類されます。他覚的耳鳴の原因として、大小の筋肉のけいれんや、血管病変の拍動などが知られていますが、自覚的耳鳴の原因はいまだに不明です。高血圧や糖尿病、疲れやストレス、睡眠不足、肩こりなどは増悪因子です。また心身症とも浅からず関連があると言われています。急性期の耳鳴には、まず難聴の原因となる疾患の治療が行われます。慢性化した耳鳴には、漢方薬の内服や精神安定剤の内服、循環改善薬やビタミン剤、局所麻酔薬の注射、鍼灸などの民間療法などが行われますが、確実に耳鳴を軽減させることは難しいとされています。その他、慢性期におこなわれる治療として、神経生理学的耳鳴理論に基づくTinnitus Retraining Therapy(TRT)や鼓室内薬物注入療法、星状神経節ブロック、自律訓練法などがあります。
耳がつまる
耳に水が入った感じ、ふたをしたような感じ、ボワーンとした感じは、外耳、中耳、内耳、いずれに原因があっても起こります。
- 外耳が原因の場合は、耳あか、綿棒の先などの異物、プールや風呂で入った水、外耳炎による外耳道の腫れや分泌物の鼓膜への付着などが原因となります。また、耳が海水と風で冷却されることで外耳道の骨が増殖し耳の穴が狭くなる「サーファーズイヤー」により外耳道が閉塞しやすくなることがあります。
- 中耳が原因の場合は、かぜに伴って鼻の奥と耳をつなぐ耳管(じかん)が腫れ、中耳の空気圧の調整がうまくできない状態(耳管狭窄症)、加齢や体重減少で耳管が開き過ぎた状態(耳管開放症)、中耳に水がたまった状態(滲出性中耳炎)などで耳のつまり感が出現します。また、飛行機に乗った時のように急激な気圧の変化に耳管の働きがついていけなくなって起こる航空性中耳炎もあります。
- 内耳が原因の場合は、低音部の内耳性難聴で耳のつまり感を訴えることが多く、金属音が耳ざわりに感じたり、ワーンといった耳なりやめまいを伴うこともあります。急性低音障害型感音(かんおん)難聴、メニエール病、突発性難聴などでよくみられる症状です。